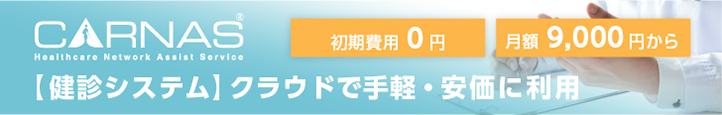医療IT最前線 第51回 ネットワーク・コミュニケーションとヒューマン・コミュニケーション
コミュニケーションは大切なテーマに
このような時代、いかに患者さんから診療所や薬局が信頼いただくことができるかが大切になっています。信頼は密接なコミュニケーションから生まれると考えます。診療所や調剤薬局にとって、いま「コミュニケーション」は大切なテーマとなっています。
医療機関同士のコミュニケーションはアナログからデジタルへ
たとえば、診療所が患者さんを病院に紹介する場合は、「診療情報提供書(紹介状)」を発行します。また、診療所が処方を薬局にオーダーする場合は「処方箋」を発行します。診療所が訪問看護ステーションに患者さんの訪問看護を依頼する場合は、「訪問看護指示書」を発行します。 このように、医療機関同士のコミュニケーションは、従来「紙」を用いて行われてきました。
しかしながら、これらの書類は、電子カルテやレセコンなどIT機器の普及が進んでいることを受けて、デジタルでやり取りすることで業務の効率化を図る動きが見られます。2025年の完成を目標に進められている「地域包括ケアシステム」を推進するために、2016年にこれらの書類をデジタルでやり取りすることが、一定のルール(地域連携ネットワークやプライベートネットワークなど、セキュリティレベルの高いネットワーク環境)の下で認められました。 いま、医療機関同士の情報共有をデジタルでやり取りする時代がやってきているのです。
電子カルテの書類作成機能を使いこなそう
電子カルテは、カルテに蓄積された情報を2次利用して、様々な書類をスピーディに作成することができるのです。 この機能を使いこなせば、診療情報提供者や診断書を即時発行することができ、「明日、取りに来てください」といった、患者さんを書類の受け取りだけで再訪させることもなくなります。書類をスピーディに発行することは診療所の差別化にもつながるのです。
患者さんに支持されるためのコミュニケーション力
昨今、接遇やコミュニケーションについて、医療機関でも重視されるようになってきました。また、患者満足度と医師による説明は、待ち時間以上に相関関係にあるという調査結果があるように、説明力、すなわちコミュニケーション力が大変重要になっています。 医療はサービス業であり、コミュニケーションや接遇は基本のスキルです。しかし、他のサービス業に比べて、命を預かる現場ですから、プライバシーに最高レベルの配慮を払い、丁寧に患者さんの立場になってコミュニケーションを行うことが求められています。
地域住民から支持される診療所になるためには、先に挙げたICT化を進めることで、「ネットワーク・コミュニケーション」を行うためのインフラを整備し、接遇やコミュニケーションを高めることで「ヒューマン・コミュニケーション」を向上させていく必要があるのです。
(2018年09月04日)![]()